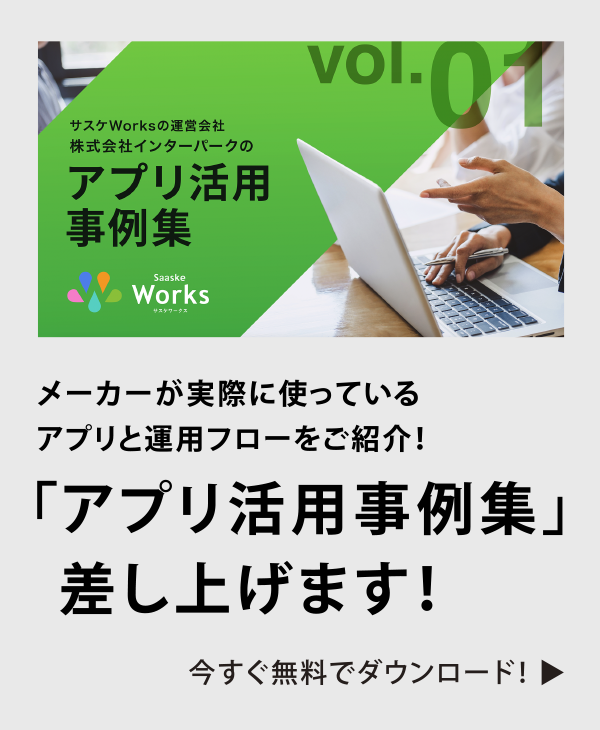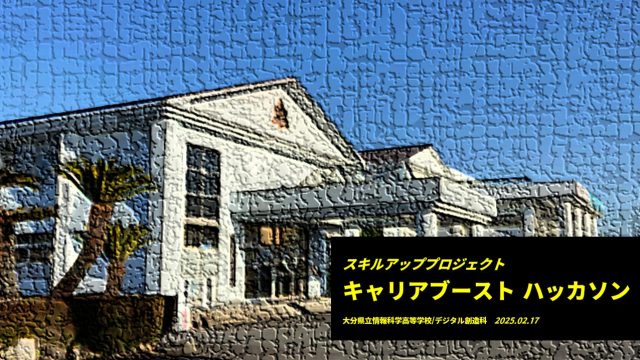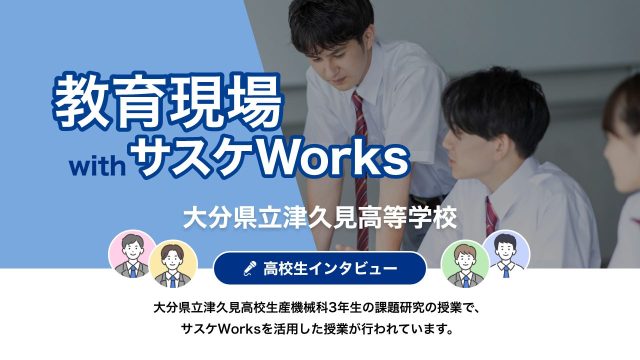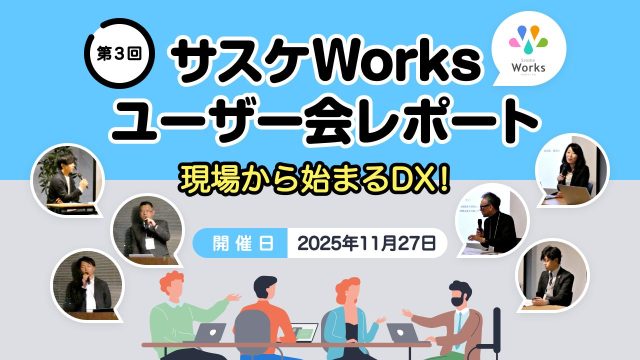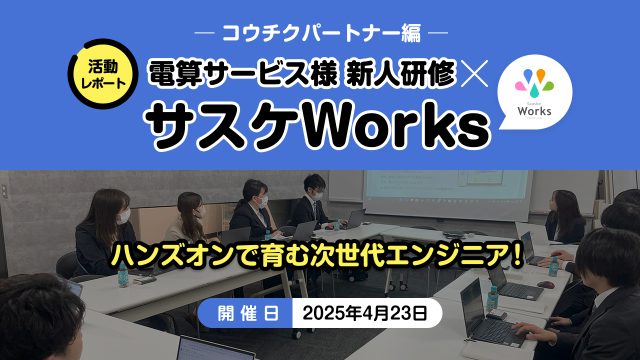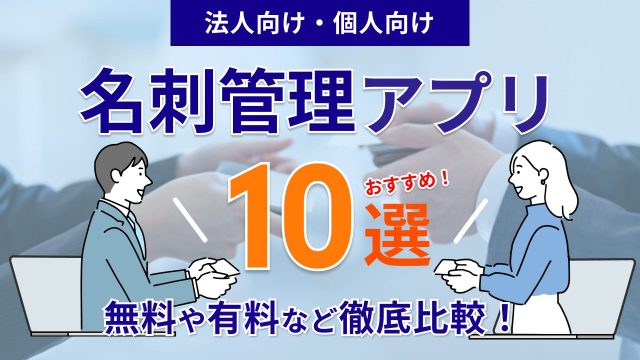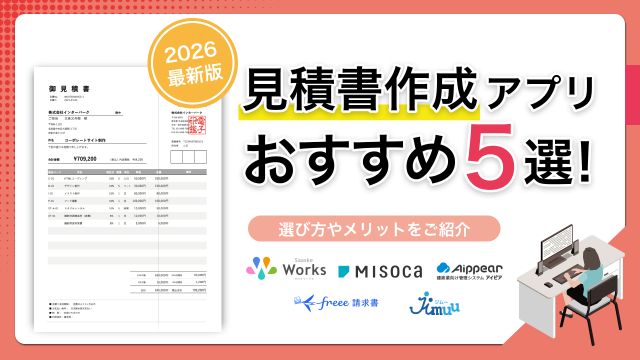小さな想いを強固な絆に。インターパークがアプリで取り組むThanksチケット制度。

【働くを真面目に考えようPROJECT】
毎年訪れる勤労感謝の日。 いつも当たり前にある「働く」を、自分、周り、社会といった様々な視点で見つめ直し、より良い働き方を目指すきっかけを作るプロジェクト。今回は、サスケWorksのメーカーである(株)インターパークの取り組みをご紹介します
本稿では、「サスケWorks」のメーカーである、株式会社インターパークが行っている、業務でのちょっとした「ありがとう」を社員間で送り合う「Thanksチケット制度」について、CEOの舩越に、経緯や想いを語ってもらいました。 (聞き手:サスケWorks広報スタッフ)。
創業時から大事にしている社内の「ありがとう」と、制度化への課題。
広報: 社長、本日はよろしくお願いします! 「働くを真面目に考えようPROJECT」ということで、社長にはインターパークで取り組んでいる「Thanksチケット制度」について深掘りさせていただきます。
CEO舩越(以下、舩越): はい、よろしくお願いします。
広報: 早速ですが、社内で使っている「Thanksチケット制度」、これはどういう経緯で始まったんですか?
舩越: はい。実は、これには大きく2つの課題があって。 まず一つは、コロナ禍によるコミュニケーション機会の減少です。もともと私には「感謝の気持ちを大切にしてほしい」という強い思いがあって、コロナ禍以前は、朝礼の際に持ち回りで“ありがとう”を発表する時間を設けていたんですよ。
広報: やってましたね!懐かしいです。
舩越: ところが、コロナ禍でリモート勤務が増えて、社員みんなが顔を合わせて朝礼を行う機会がめっきり減ってしまいました。それに伴い、そうした“ありがとう”を直接伝えるコミュニケーションの場も失われてしまったんです。
広報: なるほど。もう一つの課題というのは?
舩越: それが、当時のインセンティブ制度に対する社員のモチベーションで。これは経営陣の間でも課題になっていたんです。当時の制度は売上達成が主な評価指標だったので、どうしても売上獲得に直接関わる部署が評価されがちで…。
広報: 確かに、所属する部署によって、制度に対する受け止め方に温度差があったかもしれません…。
舩越: その通りです。バックオフィスみたいに、直接売上には関わらないけれど会社を支えてくれている大事なスタッフの頑張りが、既存の制度ではなかなか評価しづらかった。 そうした中で、「日々の小さな感謝」や「部署を越えた目に見えにくい貢献」を可視化して、もっと気軽に伝え合える仕組みが作れないか、と考えたのがきっかけですね。
感謝を「インセンティブ」に。可視化する仕組み

広報:「Thanksチケット」が具体的にはどんな制度なのか教えていただけますか?
舩越: はい。これは、社員同士が日々の業務の中での「資料作成を手伝ってくれた」「相談に乗ってくれた」といった助け合いに対して、「感謝の気持ち」を送り合えるシンプルな仕組みです。もともと紙で送っていたのですが、それをアプリ化しました。誰が誰に、どんな理由でチケットを送ったかが、アプリ上で共有されるようになっています。そして、受け取ったチケットの枚数に応じて、ささやかですが社員が実際にインセンティブを受け取ることができるようにしています。
広報:その仕組みを、あえて、という言い方は変ですが(笑)自社のサスケWorksで構築したのはなぜですか?
舩越: 当時サスケWorksはリリースされた直後でして。まずは社内でも積極的に利用していこうというトライアルとしての側面もありました。このThanksチケット制度は、まさにサスケWorksの「アイデア次第でどんなことにも活用できる」という特長と、アプリをプログラミング不要で「素早く簡単に作れる」という特性がぴったりマッチする案件だと感じたんです。
広報:なるほど、まさに自社製品で実践したわけですね。
舩越: はい。だから、この「Thanksチケット制度」のアイデアが生まれてから、アプリとして実働するまでが本当に早かったですね。何にでも対応できるサスケWorksだからこそ、こうした社内の小さな「やってみたい」をすぐに形にできました。
拠点を超えて深まる「小さな絆」
広報:導入してみて、社員のみなさんの反応はどうでしたか?
舩越: それが、紙の方がいいとか既存支持の意見もあるかと思ったのですが、まったく不
満がでることなくとても好評で。「資料作成を手伝ってくれてありがとう」といった業務上のことから、「お菓子ごちそうさま」といった日常の些細なことまで、小さな気づきや感謝を具体的に伝えられることが受け入れられているんだと思います。
広報: 拠点間のコミュニケーションにも変化はありましたか?
舩越: はい。目に見えて増えましたね。アプリ上で「誰が誰に感謝しているか」が見えるから、普段接点の少ないスタッフ同士の意外な繋がりが分かったりもして(笑) 東京・札幌の拠点間でのチケットのやり取りも確実に増えていると感じています。
広報:社長は「働く」上で、そういう人と人との関係性をすごく重視されていますよね。
舩越: 強く意識していますね。どんな仕事であれ、それを行うのは「人」ですから。仕事をする以上は、人と人の関係は大事にすべきだと考えています。このThanksチケットのような、本当に「小さなこと」の積み重ねが、結果として会社の強固な絆を作っていくんだと信じています。
広報:インターパークはIT企業ですけど、「人」を大切にするマインド、すごく感じます。
舩越: ありがとうございます。インターパークはITの会社ではありますが、事業の根幹は常にお客様やスタッフといった「人」との関係性です。だからこそ、どれだけテクノロジーが進化しても、人やコミュニケーション、感謝を大事にするマインドは、絶対に失ってはいけないと思っています。拠点を超えて深まる「小さな絆」を大事にしたいです。
社員発のアイデアが育む、次のチャレンジ
広報:このThanksチケットアプリ、今後の展望があれば教えてください。
舩越: 嬉しいことに、スタッフたちから「せっかくのありがとうの言葉を、社内広報などで活用しよう」という意見も出てきて、もう準備を進めてくれているんですよ。 先日は技術スタッフの勉強会で「社内通貨システム」の構想を発表したスタッフがいて、その中でThanksチケットを組み込めないかなんて話も出たとかで(笑)
広報:社内通貨システム!それは夢が広がりますね!
舩越: ええ、実現できるかは分かりませんが(笑)。でも、こうして何か1つを始めることで、ほんの小さなコミュニケーションが生まれる。そして、それが人の肌感覚を持った、温かい広がりに繋がっていく。 このThanksチケット制度は、会社としては小さな取り組みかもしれませんが、当社の誇るべきチャレンジだと感じています。
社員発のアイデアが育む、次のチャレンジにも期待したいですね。
ノーコードとAIで、「より良い時間」を創出する!
広報:最後に、このプロジェクトに寄せてメッセージをお願いします。
舩越: 「働く」というのは、突き詰めれば「誰かの役に立つ」ことだと思います。このアプリを通して、スタッフ同士が「役に立ててありがとう」と感じ合う輪が、それを伝えあえる関係が、もっと広がっていってほしいと願っています。
私たちはIT企業として、サスケWorksのようなノーコードツールや、これからのAI技術を活用することで、日常業務の無駄を省き、より良い時間を創出できるはずだと考えています。実際に社内でも技術部門による「AI勉強会」が立ち上がっており、そこで得た知見を社内の業務改善や我々のプロダクト自体にフィードバックするために活発に活動してくれていますしね。
そうして生まれた時間を、さらに付加価値の高い業務に充てることも、あるいはプライベートを充実させることに使うこともできる。人々がそうして業務もプライベートも充実させていくことができる未来を作っていくための手段を提示することが、我々の存在価値だと思っています。
サービスメーカーであるインターパークが、そういった活動を率先して進めていき、より
良い「働く」の形を社会に示していきたいですね。
広報:勤労感謝の日に、「感謝」の循環が「働く」ことの原動力になるという、とても良い話を私自身が社長から直接聞けて嬉しいです(笑)。社長、本日はありがとうございました!
サスケ Works「働くを真面目に考えよう PROJECT」特設サイトはこちら
https://works.saaske.com/lp/24/