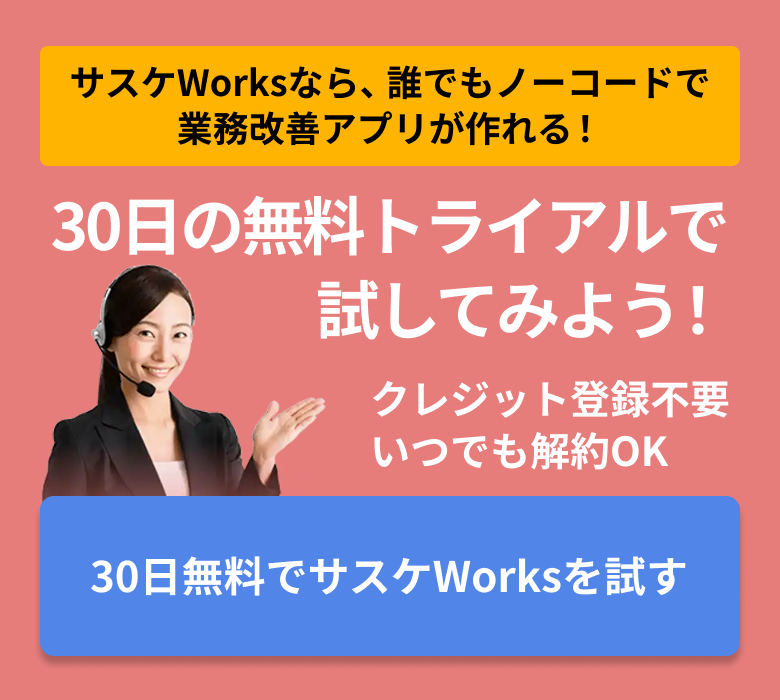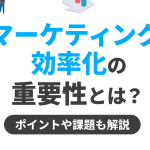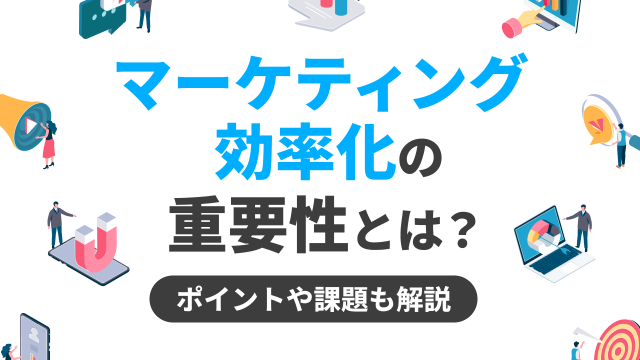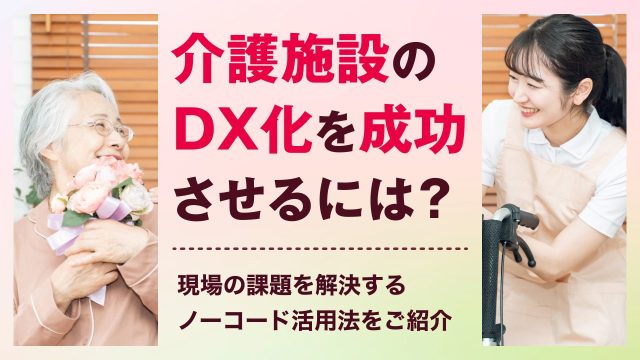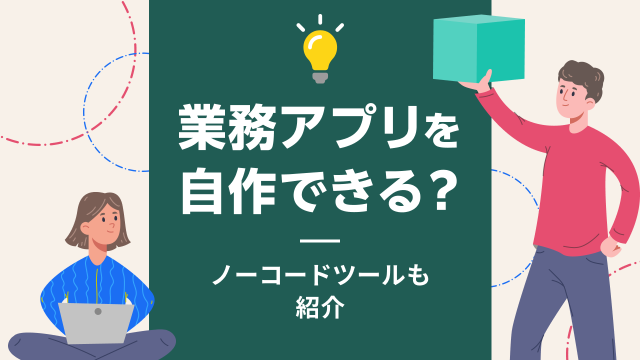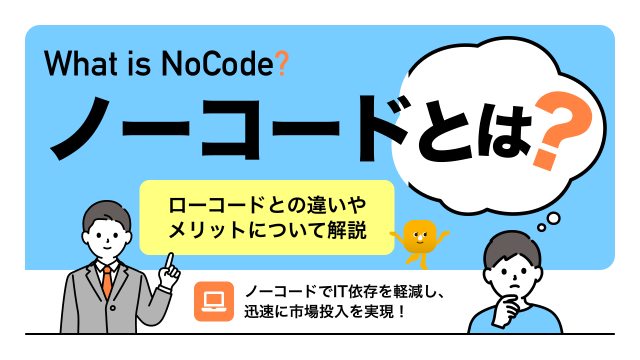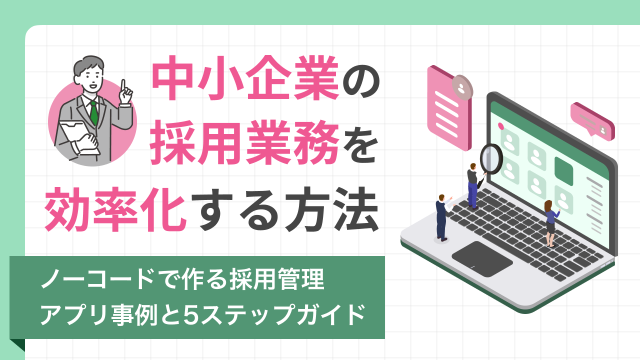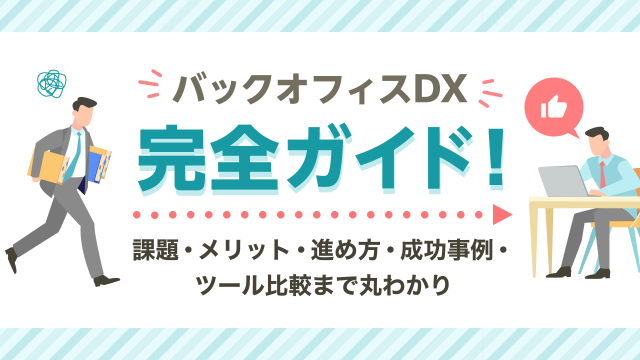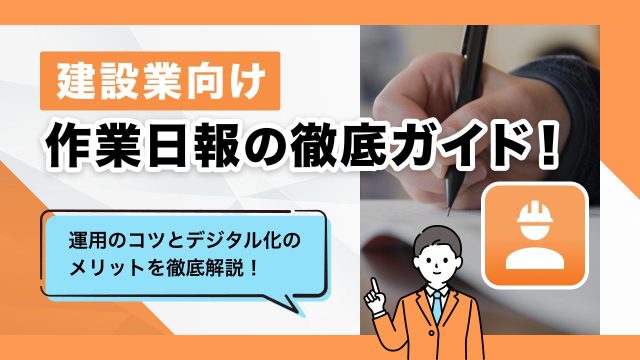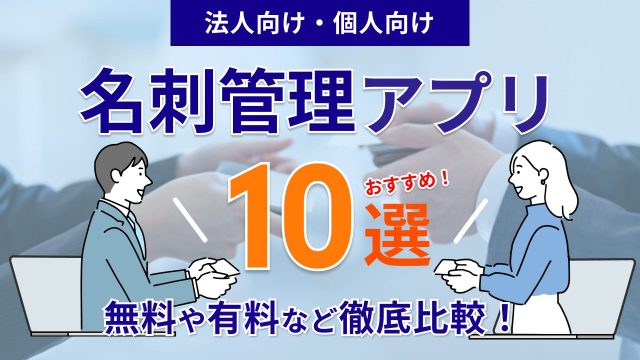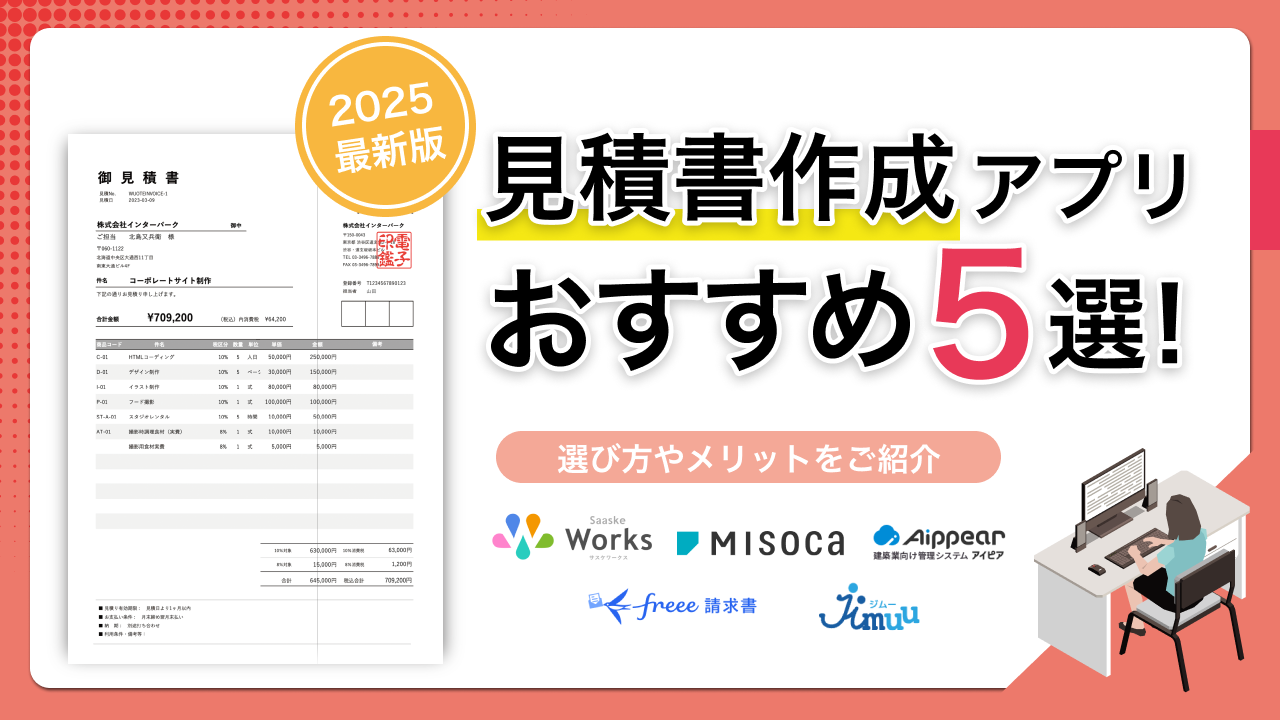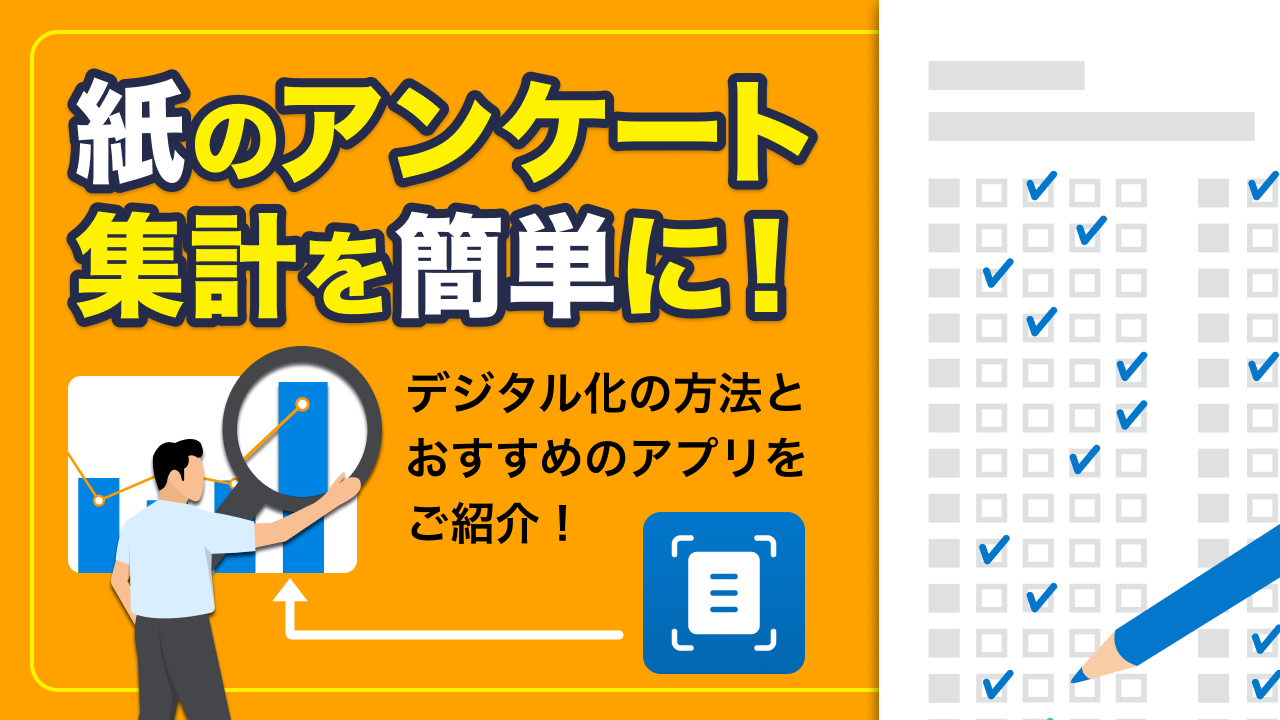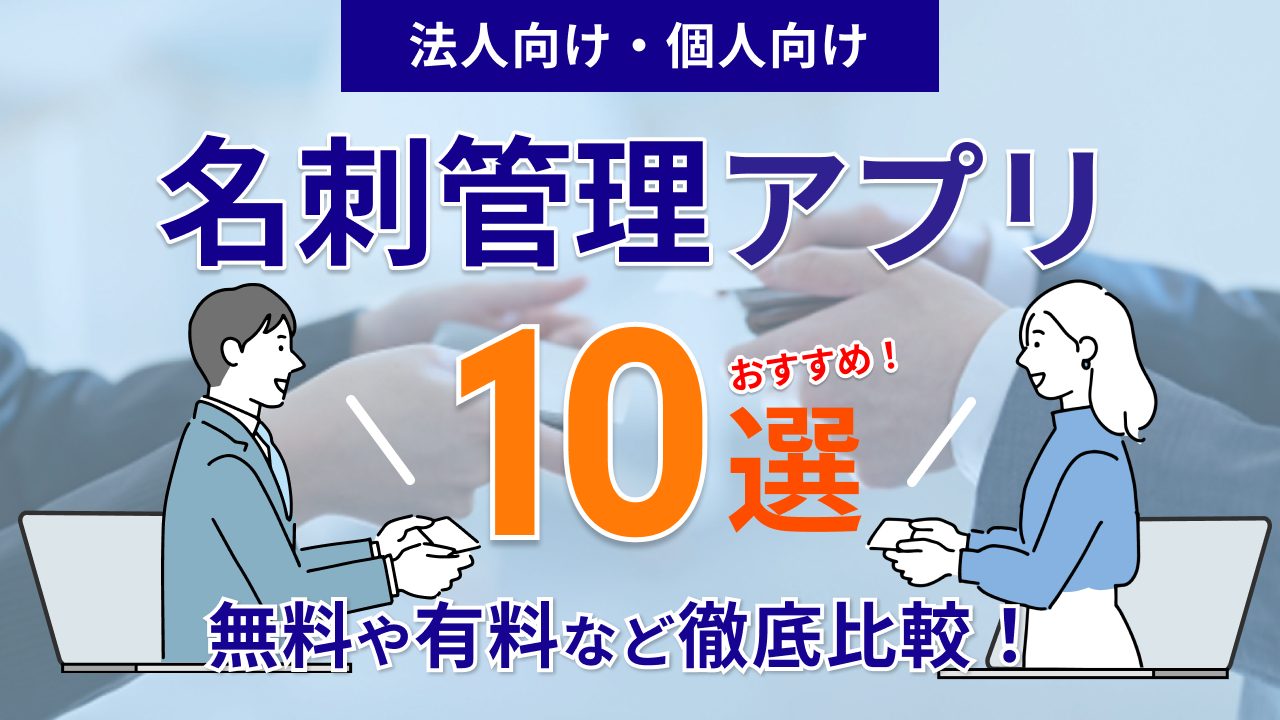紙カルテを電子化するには?移行時の課題とノーコードで解決する方法
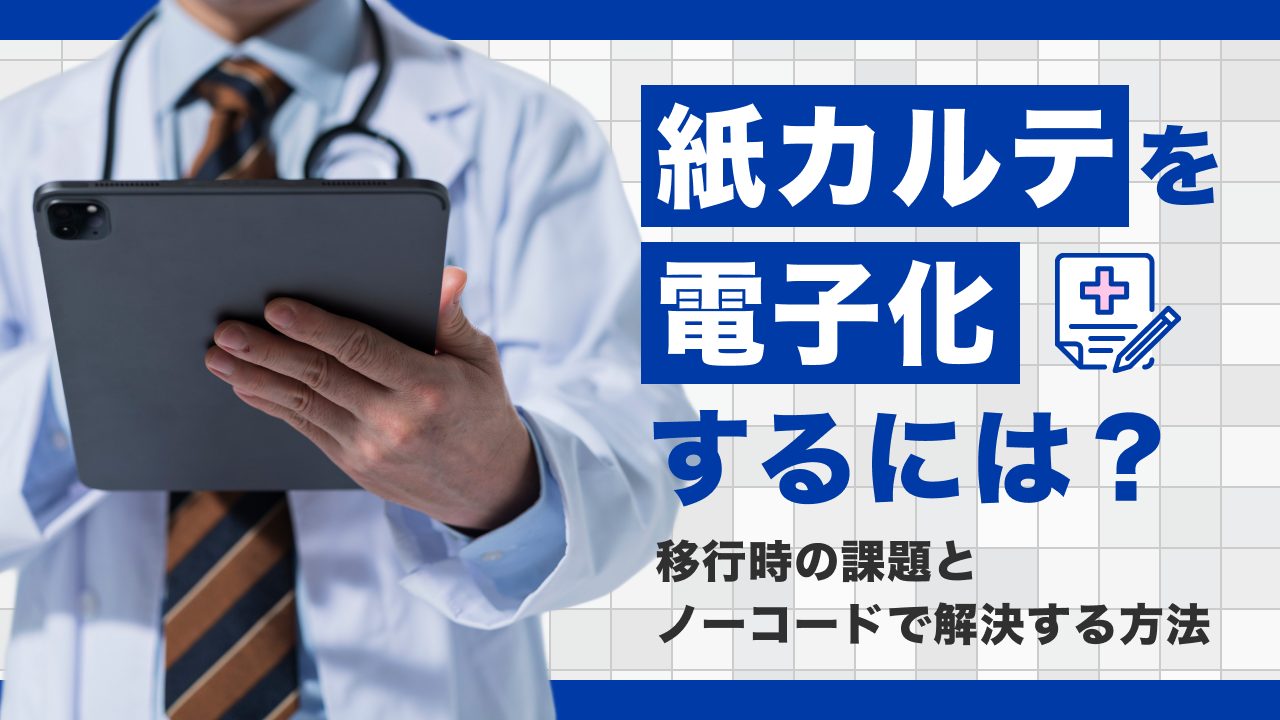
紙カルテの管理に限界を感じていませんか?
電子化を検討していても、「どうやって進めればいいのか」「費用や作業量はどれくらいか」など、不安を感じている方も多いはずです。
この記事では、紙カルテ電子化の手順や課題、そしてノーコードツールによる効率的な移行方法について解説していきます。
紙カルテの電子化とは?
紙カルテの電子化とは、過去に紙で保存されていた診療記録や患者情報を、デジタルデータに変換して管理することを指します。
これにより、手入力での記録作業から解放され、業務効率や情報の活用性が大きく向上します。
一般的に「電子カルテ」というと、診療行為をその場で入力・保存するシステムを指しますが、紙カルテの電子化はその第一歩であり、過去の記録をスキャン・データ化して保管しやすくする作業が中心です。
最近では、医療のIT化が進む中で厚生労働省も電子化の必要性を示しており、地域の中小クリニックでも導入が進みつつあります。
特に、業務の効率化やペーパーレスの流れが加速している今、紙カルテの電子化は避けて通れないテーマとなっています。
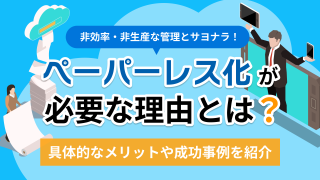
紙カルテを電子化するメリットと課題
紙カルテの電子化は、業務効率や情報管理の向上につながる一方で、導入にあたってはさまざまな課題も伴います。
このセクションでは、電子化によって得られるメリットと、事前に知っておきたい注意点について整理します。
電子化によって得られる主なメリット
電子化によってまず得られるのは、紙の保管スペースの削減と必要な情報をすぐに検索できる利便性です。
これまで膨大なカルテの中から探していた時間が短縮され、業務効率が大幅に向上します。
また、電子化された情報は複数の端末からアクセスできるようになるため、他のスタッフや拠点との情報共有もスムーズになります。
さらには、火災や水害などの災害時にもデータのバックアップがあれば復旧しやすく、セキュリティ面でも安心です。
注意すべき課題・デメリット
一方で、電子化には事前の準備と一定の手間がかかります。
スキャン作業やデータ整理には時間と人手が必要で、通常業務と並行して進める場合は負荷が大きくなりがちです。
また、電子化の移行期間中は紙とデジタルの両方を扱う必要があり、オペレーションが一時的に複雑になることがあります。
さらに、電子カルテとの連携がうまくいかない場合、重複入力などの手間が発生する可能性もあるため、ツールの選定や運用設計が重要です。
紙カルテ電子化の流れ
紙カルテの電子化は一度にすべて完了するものではなく、いくつかの段階を踏みながら進めていく必要があります。
このセクションでは、実際に電子化を行う際の基本的なステップをご紹介します。
1.電子化の方針と対象範囲の決定
まず最初に行うべきは、「何を」「どこまで」電子化するかを明確にすることです。
たとえば、すべてのカルテを対象とするのか、直近数年分に限定するのかを決めておくことで、作業の見通しが立てやすくなります。
無理のない範囲から始めることで、スムーズなスタートを切ることができます。
2.紙カルテのスキャン・データ化作業
次に行うのが実際のスキャン作業です。
業務用のスキャナーを使用して紙カルテをデジタル化し、OCR(文字認識ソフト)で文字情報として読み取ることで、後から検索や分類が可能になります。
スキャンの精度やデータ形式も後の活用に大きく影響します。
事前に運用イメージを共有し、作業基準を統一しておくことが大切です。
3.データの整理と管理ルールの整備
スキャン後は、データを保管・活用するための管理ルールを整えていきます。
ファイル名の付け方や保存フォルダの構成、アクセス権限の設定などを明確にしておくことで、後からの混乱を防げます。
データを“使える状態”にしておくことが、電子化の成果を最大限に活かすポイントです。
4.電子カルテや業務アプリとの連携
最後に、スキャンしたデータをどう活用していくかを考えましょう。
電子カルテとの連携が可能であれば、より一元的な情報管理が実現しますし、ノーコードの業務アプリを使えば、検索や記録・共有といった運用を柔軟に設計できます。
こうした活用方法は紙からの移行を単なる保存作業ではなく、業務全体の効率化につなげる鍵になります。
紙カルテ電子化を進める上での注意点と成功のコツ
電子化は一度始めると後戻りが難しいため、スムーズに進めるための準備が欠かせません。ここでは、電子化を成功させるために押さえておきたいポイントをご紹介します。
現場に合った進め方を選ぶことがカギ
電子化には「一括で全てを移行する方法」と「一部から段階的に始める方法」があります。どちらが適しているかは、現場のリソースやカルテの量によって異なります。
負担を減らすには、まず直近のカルテやよく参照する診療科から始める方法が現実的です。
また、一定期間は紙と電子の併用を前提に設計することで、現場の混乱も最小限に抑えられます。
運用ルール・アクセス管理の整備も重要
電子化によって情報がデジタル化されるとアクセスのしやすさが一気に向上しますが、一方でセキュリティ対策や操作ルールを明確にしておく必要があります。
たとえば、誰がどのデータにアクセスできるか、誤って削除された場合のバックアップ体制など、事前にルールを決めておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
「使いやすい」だけでなく「安全に使える」環境を整えることが成功のカギとなります。
紙カルテ電子化に活用できる「サスケWorks」の特徴
紙カルテを電子化したあと、データをどのように活用するかが重要です。
ここでは、ノーコードでアプリを構築できる「サスケWorks」の特徴をご紹介します。
サスケWorksとは?

サスケWorksは、専門知識がなくても自分たちに合わせた業務アプリを作成できるクラウドサービスです。
AI-OCR機能があるため紙カルテをスキャンし、データとして保存することができます。
医療機関での導入実績もあり、診療記録や報告内容を整理するツールとして活用されています。
また、30日間の無料トライアルも提供されているため、まずは小規模な用途から試すことが可能です。
実際に作ってみたい方は、30日間の無料トライアルをぜひお試しください。
よくある質問(FAQ)
紙カルテから電子化するのにいくらかかりますか?
費用はカルテの件数や電子化の方法によって大きく異なります。
スキャン作業を外部に委託するか院内で対応するかでも変動がありますが、一般的には数十万円〜数百万円の予算を想定するケースが多いです。
段階的に進めたり、必要な部分だけを対象にすることでコストを抑えることも可能です。
電子カルテと紙カルテの併用は可能ですか?
はい、可能です。
実際、多くのクリニックでは移行期間中に併用するケースが見られます。
一部の診療科や特定の期間に限定して電子化を進めることで、無理なく導入できるメリットがあります。
ただし、情報の重複や記録ミスを防ぐためには運用ルールの整備が必要です。
なぜ電子カルテはすぐ普及しないのですか?
理由はいくつかありますが、主にコストや運用の難しさが挙げられます。
小規模なクリニックでは高額なシステム導入が負担となるほか、職員のITリテラシーに不安を感じているケースも少なくありません。
そのため、まずは紙カルテの電子化から始めて、段階的に環境を整えていく方法が現実的です。
電子化によるセキュリティ対策は大丈夫か?
セキュリティは非常に重要なポイントです。
データの保存方法やアクセス制限、定期的なバックアップを設けることで安全性を高めることができます。
クラウドツールを活用する場合でも信頼性のあるサービスを選び、院内での運用ルールを明確にすることが大切です。
ノーコードツールは医療現場でも使えますか?
はい、使えます。
近年では医療業界でもノーコードツールの導入が進んでおり、記録・報告・検索などの定型業務を簡単にアプリ化することが可能です。
たとえば、サスケWorksのようなノーコードツールを使えば、専門知識がなくても業務に合ったアプリを短期間で構築できます。
紙カルテ電子化を成功させ、業務の効率化を実現しよう
紙カルテを電子化することは、単なる作業のデジタル化ではなく、業務全体を見直す大きなチャンスでもあります。
手間やコストが気になる方も多いかもしれませんが、あらかじめ進め方や注意点を理解しておけば、現場に合った形で無理なく移行を進めることができます。
また、ノーコードツールを活用すればデータを蓄積するだけでなく、検索や集計・共有まで含めて、現場主体で柔軟に設計・運用することが可能です。
まずは業務アプリを1つ作ってみませんか?
サスケWorksなら今すぐ無料で始められます。
著者情報

-
ノーコードWEBアプリ作成ツール「サスケWorks」のオウンドメディアです。
ノーコード技術やアプリ開発に関する情報や初心者向けの使い方、活用事例など、皆さまの業務効率化に役立つ情報をお届けしています。
ノーコードでのアプリ作成に興味がある方や業務改善を目指している方に向けて、実践的なノウハウをわかりやすくご紹介していきます。
最新の投稿
 Worksを知る2025年12月25日マーケティング効率化の重要性とは?ポイントや課題も解説
Worksを知る2025年12月25日マーケティング効率化の重要性とは?ポイントや課題も解説 Worksを知る2025年12月25日会計事務所のDXとは?必要性・課題・進め方をわかりやすく解説
Worksを知る2025年12月25日会計事務所のDXとは?必要性・課題・進め方をわかりやすく解説 Worksを知る2025年12月12日AI-OCRのおすすめ5選を比較!選び方や導入時のポイントを解説
Worksを知る2025年12月12日AI-OCRのおすすめ5選を比較!選び方や導入時のポイントを解説 Worksを知る2025年12月1日業務の属人化を解消するには?原因やデメリット、解消のステップを徹底解説
Worksを知る2025年12月1日業務の属人化を解消するには?原因やデメリット、解消のステップを徹底解説